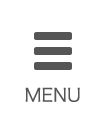研究プロジェクト
研究プロジェクト
また、内分泌学、神経内分泌学的観点から、成長、発達を制御する機構と発達障害に関する研究を行っています。
上記目的のため、研究所の各研究部ならびに病院の様々な診療部との連携を図りながら、臨床検体を用いた検討を行うとともに、遺伝子改変動物等による病態モデル動物、疾患モデル細胞の作成・解析、株化細胞、初代培養細胞、iPS細胞などの組織培養・細胞培養による病態の再現による前臨床試験に向けた研究、治療薬候補の探索、薬物試験の動物実験代替法に関する研究を推進しています。外部研究機関との共同研究も行い、多角的な観点から成育医療に対する薬剤治療研究を行っています。
1. ヒト検体を利用した薬剤治療研究基盤の構築
1)薬剤治療に資する肝細胞研究
従来は動物細胞や動物個体を用いた実験を行い、開発過程での医薬品の薬理効果や副作用の有無等を解析していました。しかし、動物を用いた評価はヒトへの外挿性の問題が指摘され、動物実験で検証された化合物が実際にヒトへ投与されると予期しない副作用が発現したり、複数の薬の相互作用による副作用が発現することが報告されています。特に、体内での薬物の代謝は肝細胞の薬物代謝機能に依存するものが多く、創薬研究や薬物動態研究においてヒトの肝機能発現に関する検討は極めて重要な研究課題となっています。他の臓器・細胞を対象とした研究と同様に、肝細胞/肝機能の研究においても培養系でのヒト肝細胞の検討が有効であると考えられますが、肝細胞は単離・培養により肝特異的機能が急速に減衰し、初代培養系では生体内の肝機能を維持することは難しい現状があります。また、一般的に不死化した肝細胞株は肝特異的機能を有してはいるものの、その機能は著しく低いことが知られています。この様な背景より、培養系における肝細胞/肝機能に関する研究は、他の組織・細胞に比べ困難です。
培養過程における肝細胞の機能低下は、組織分散・細胞単離による組織形態の崩壊と細胞間コミュニケーションの消失が原因と考えられます。培養系において肝機能を維持する試みとして、これまでにマトリゲルによるサンドイッチ培養法や細胞塊を形成させる等の組織構造を模倣するような三次元培養系が検討されてきました。薬剤治療研究部ではこれまでに肝細胞株HepG2細胞の肝機能亢進を目指し、新規三次元培養法を開発し、HepG2細胞の肝機能を亢進させることに成功しています。さらにHepG2細胞において培養液中にDNAメチル化阻害剤であるゼブラリンを添加することにより、薬物代謝酵素の遺伝子発現が亢進することを見出しました。その機序として、ゼブラリンによるDNAメチル化酵素の阻害とdouble-stranded RNA (dsRNA)-activated protein kinase (PKR)の抑制が薬物代謝酵素遺伝子発現に関与することを明らかにしました。さらに薬物代謝酵素の発現亢進に伴い、薬物代謝産物による肝障害への感受性の増強を確認してきました。これらの知見から、三次元培養、薬物添加、遺伝子導入等の手法を組み合わせることにより、さらなる培養肝細胞の機能が亢進可能となり、より感度・特異性の高いin vitro薬物毒性・安全性評価系の構築が可能となると考えられます。これまでの成果を元に、DNAメチル化酵素であるDNMT1とPKRをダブルノックダウンしたHepG2細胞改変株(HepG2-DP細胞)を樹立しました。HepG2-DP細胞では薬物代謝酵素であるCYP1A2やCYP2C19の他、アルブミンの遺伝子発現量の有意な増加が認められました。
一方、上述のように、平面培養と比較して、スフェロイド培養あるいは三次元培養は肝特異的機能を向上させます。これらの成果からも、肝細胞としての機能を発現する為には細胞間接着と細胞の極性が重要であると考えられます。HepG2細胞は低密度で培養するとコロニー状に増殖し、細胞間の接着面積が増加します。薬剤治療部では、低密度で培養したHepG2細胞でCYP及びアルコールデヒドロゲナーゼ、胆汁酸トランスポーター(MRP2)、胆汁酸抱合酵素(BAAT)の遺伝子発現が有意に増加することを見出しています。また、低密度で培養したコロニー状のHepG2細胞ではタイトジャンクション関連タンパク質(ZO1, Occludin, Tricellulin)の発現が増加することを見出しています。siRNAによるOccludinとTricellulinのノックダウンは低密度培養による肝特異的遺伝子の発現誘導を有意に抑制しました。これらの知見は、肝細胞機能制御に細胞間接着が重要であることを示しています。今後はOccludin及びTricellulinの過剰発現によってHepG2細胞の機能が亢進するか検討を進める予定です。
2)創薬研究に活用可能なヒト組織・細胞材料の開発
薬剤治療研究部では、倫理委員会承認の下、生体肝移植時のレシピエント摘出肝やドナー余剰肝より、日本人ヒト肝細胞の単離・保存・培養を行っています。これまでに300例を超える手術摘出肝より肝細胞の単離を行っています。これまでの単離経験から、単離した肝細胞で培養基材に接着性を有する肝細胞の割合はきわめて低い事がわかりました。市販の凍結肝細胞においても、接着性/非接着性ロットが販売されていますが、非接着性ロットに比べ接着性ロットは種類が少なくかつ高価です。通常、薬物相互作用や化合物による薬物代謝酵素誘導作用を検討するためには接着肝細胞を用いるため、非接着性のロットを接着培養することができれば、より多くのロットにより試験が実施でき、かつ安価な非接着細胞を用いることが可能となり、試験効率とともにコストパフォーマンスの向上にもつながります。薬剤治療研究部では単離ヒト初代培養肝細胞の接着性について検討を行っています。接着性/非接着性初代培養肝細胞間で、マイクロアレイによる細胞接着関連遺伝子の網羅的解析を行い、両細胞の特性の差を検証した結果、非接着性の肝細胞において発現低下が見られる接着因子を同定し、特定の細胞外マトリクスを含む混合コート上で肝細胞培養する事で、初代培養肝細胞の接着性が向上する事を明らかにしました。創薬における開発化合物の安全性および薬物動態を検討する上で、これら成果は培養系における高機能な肝細胞の提供につながる成果であり、薬剤治療研究における意義及び波及効果は大きいと考えられます。
創薬における開発化合物の安全性および薬物動態を検討する上で、これら成果は培養系における高機能な肝細胞の提供につながる成果であり、薬剤治療研究における意義及び波及効果は大きいと考えられます。
2.成育疾患としての下垂体細胞分化機構の研究
1) 下垂体ホルモン産生細胞分化・増殖制御機構の解析
内分泌系において中枢組織と末梢組織のインターフェースとして働く下垂体前葉からは、6種類のホルモン;成長ホルモン(GH)、プロラクチン(PRL)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、黄体形成ホルモン(LH)、濾胞刺激ホルモン(FSH)が視床下部因子および末梢器官からのフィードバック制御の下に分泌され、末梢の標的器官の機能を制御しています。例えば、GHは小児期の成長に重要であるとともに、成人においても脂質代謝、筋肉、骨量、心血管などで重要な役割を果たしています。GH分泌不全症では、肥満、糖尿病、骨粗鬆症、心筋梗塞のリスクが高まります。日常生活においても集中力・記憶力の低下や疲労、気力の低下など、精神面に影響を与えています。このようなGHの臨床上の重要性から、日本ではGH分泌不全患者に対して、2006年からGH製剤の皮下注射が保険適応となっています。しかし、治療費が高額であることからやむを得ず中断する患者も多く存在します。下垂体は一度損傷すると自立的再生が不可能であり、その重篤性から下垂体ホルモン分泌不全症は難病に指定されています。下垂体ホルモン分泌不全患者に対する治療には一般的にホルモン補充療法等の対処療法が行われますが、ホルモン補充療法では日内変動やストレス下における応答を再現するのは難しく、成長期や思春期の成長段階に応じた調整が必要となるなどの理由から、ホルモン補充療法に代わる根治療法が求められています。
近年マイクロRNA(miRNA)による遺伝子発現・翻訳制御機構と生体恒常性維持・疾患発症との関連が注目されています。薬剤治療研究部では新規創薬標的としてのmiRNAによる生体機能制御機構の解明として、下垂体の細胞分化・機能制御におけるmiRNAの機能について検討を行っています。GH非産生細胞とGH産生細胞におけるmiRNA発現プロファイルを比較し、GH産生細胞において発現が高い複数のmiRNAを同定しました。さらに、これらmiRNAをGH非産生細胞へ発現させ、GH産生を制御するmiRNAを同定しました。GH産生細胞特異的に成熟miRNA合成を阻害したマウスでは、低体重を示し、下垂体の矮小化を呈することを明らかにしました。これらの結果から、miRNAはGH産生を制御し、個体の成長に重要な役割を有することが示唆されます。この知見は、miRNAの機能制御が下垂体機能低下症の治療標的になる可能性を示しています。
3. 社会性行動の分子基盤に関する研究
1) 親親子間の社会性行動調節機構・愛着障害発症機構の解明・薬物療法の開発
脳下垂体後葉ホルモンには、オキシトシンとバソプレシンが存在し、末梢作用に加えて中枢神経系においても学習・記憶や社会行動、愛情・不安・抑うつ、知覚・痛覚など様々な生理機能に関与していることが明らかになっています。オキシトシンは母性ホルモンとして抗不安、抗うつ効果を発揮し、バソプレシンは父性ホルモンとして不安・抑うつ関連行動を増加させることが報告されています。幼少期に親子間の相互的な愛情やスキンシップのやり取りができていないと、オキシトシンの分泌が低下し、愛着障害が発症しやすくなると考えられています。オキシトシンの分泌低下は、不安感や孤独感を増悪し、ストレス耐性が弱く他者不信・攻撃性が強い傾向につながると考えられています。また、子育て中の母親はオキシトシンレベルが高く、不安感が減少するが、幼少期の虐待経験をもつ女性はオキシトシンレベルが低く、不安スコアが高いと言われています。一方、バソプレシンはオスのつがい形成や父性愛を生み出すホルモンとして知られ、バソプレシンの分泌とバソプレシン受容体の数・感度は、幼少期の親子関係・養育環境に大きく影響を受けると考えられています。オキシトシンはストレスや不安感を和らげて落ち着ける作用を持っているのに対して、バソプレシンは愛する妻や大切な子供を守るために攻撃性・行動力を高めるといった異なる作用も持っています。
母性/父性ホルモンとして知られるオキシトシン(OXT)/バソプレシン(AVP)機能を検討するため、研究部ではこれまでにバソプレシン受容体(V1a受容体、V1b受容体)トランスジェニックマウス、バソプレシン受容体(V1a受容体、V1b受容体)遺伝子欠損マウスを作成してきました。さらに、バソプレシン受容体(V1a受容体、V1b受容体)遺伝子領域をCreリコンビナーゼ標的配列loxPで挟んだ遺伝子座を持つマウス(floxマウス)を作出し、共同研究等によりAVP-floxedマウス、オキシトシン受容体-floxedマウス、オキシトシン分泌制御因子であるCD38遺伝子のKOマウスを入手・維持しています。同時に細胞選択的遺伝子欠損を生じさせるための各種Creリコンビナーゼマウスを入手してきており、世界でも最も多くのオキシトシン/バソプレシン関連因子遺伝子改変マウスを有する体制を整えてきました。これまでに、これらのOXT/AVP関連因子遺伝子改変マウスを用いてバソプレシンによる社会行動に及ぼす影響について解析を行ってきた結果、V1a受容体及びV1b受容体の両方を欠損したマウス(V1a/V1bR-KOマウス)では、野生型やV1aR-KOあるいはV1bR-KOマウスに比べ新規環境への適応が著しく低下していることを明らかにしました。このV1受容体欠損マウスで見られる社会性行動の障害は、自閉症スペクトラムの主症状と一致すると考えられます。
さらに、共同研究により行動制御にけるバソプレシンの機能をバソプレシンの脳内における2種類の受容体、V1a受容体、V1b受容体 をダブルノックアウト(dKO)した雄マウスと野生型(WT)雄マウスの行動を比較し解析しました。性行動テストにおいてdKO雄マウスはWT雄マウスに比べ雌に対する追従回数が多く、またマウント回数も多いことを見出しました。同時に不安行動の評価のために、オープンフィールド(OF)テストや高架式十字迷路(EPM)を含む複数のテストを行ったところ、dKO雄マウスの不安様行動はWT雄マウスに比べて低いことを見出しました。従って、dKO雄マウスでは不安行動が低減され、性行動の亢進に寄与したと考えられました。これらの結果は、バソプレシン受容体が不安行動を制御し、さらに性行動にも影響を与えることを示しており、家族間の行動調節機構の理解に重要な知見であると考えられます。
親子間の社会性行動調節機構として、子の母親への愛着形成に関する神経基盤を解明するため、実験動物モデルを用いた検討を行っています。幼若マウスを用いて、母親あるいは見知らぬ雌(新奇雌)のいずれに選好性を示すかを評価する母親選好性試験を行い、仔マウスを、母親に対して高い選好性を示す群と見知らぬ雌に対して高い選好性を示す群に分類しました。これら群において、母親との接触時の神経細胞の活性を比較したところ、脳内の前帯状皮質と分界条床核領域において神経細胞の活性化に変化があることを見出しました。特に、前帯状皮質ではグルタミン酸作動性神経が見知らぬ雌にに対して高い選好性を示す群で有意に活性化していました。これらの結果から、前帯状皮質および分界条床核が仔の母親選好性を制御していることが示唆されます。