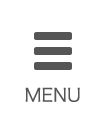- トップ
- > 患者・ご家族の方へ
- > 病気に関する情報
- > 子どもの病気
- > 小児炎症性腸疾患(IBD)
- > クローン病
クローン病
クローン病とは
炎症性腸疾患(IBD)に分類されるクローン病は、持続する炎症が消化管に生じる病気で、粘膜に潰瘍やびらん(ただれ)ができてしまいます。アメリカのクローン医師が初めて報告したので「クローン病」という病名になりました。発症すると、腹痛や下痢、血便、体重減少などの症状が現れ、良くなったり悪くなったりを繰り返します。原因不明の発熱や成長障害などの症状で気付かれることもあります。炎症は、腸だけでなく、口から肛門まで広範囲の消化管に生じ、炎症が強い場所によって現れる症状が異なります。治療が不十分で、病気が進行すると、腸が狭くなったり(狭窄)、腸に穴があいたり(穿孔)するなど重篤な状態になることがあります。現在のところ、クローン病の原因は分かっていませんが、本来外敵に対して働く免疫システムが、自分の消化管を異常に攻撃している状態といわれています。発症する患者さんの数は年々増加しており、15歳から35歳頃に診断されることが多いのですが、乳幼児期を含む小児期に発症することも珍しくありません。小児期発症のクローン病であっても、成人患者さんと同様の検査や治療を行うことになりますが、小児特有の留意点も少なくなく、特に成長期までの小児患者さんでは、小児IBD診療に精通した施設での診療が望まれます。
血液検査や便検査などに加えて様々な画像検査を組み合わせることで、総合的にクローン病の病状を把握しています。特に、炎症の範囲や程度を調べるためには、内視鏡検査で粘膜の状態を観察することが大切です。当センターは、国内では数少ない子どものための内視鏡施設として、赤ちゃんから大人まで幅広く内視鏡診療を提供しています(年間内視鏡件数)。乳幼児では、安全性に配慮して全身麻酔下で内視鏡検査を行うことが多いのですが、学童期以降の年長児では、点滴からの鎮静剤・鎮痛剤を適切に使うことで、眠っている間に苦痛を最小限にして検査を行っています。また、従来の内視鏡検査では観察が難しかった小腸に対しても、当センターでは小腸カプセル内視鏡やダブルバルーン小腸内視鏡を使い、精度の高い診療を行っています。

消化管内視鏡
クローン病による下痢や腹痛をコントロールするには、治療が不可欠です。治療をしないでいると、腸が狭くなったり、腸に瘻孔(ろうこう)と呼ばれる穴があいてしまったりして、手術を要する状態になることもあります。
現在のところ、クローン病を根治させることはできません。しかし、治療によって、良い状態(寛解と言います)を保つことで、多くの場合、学校生活(授業や修学旅行など)や課外活動などに積極的に取り組むことができます。
寛解を保つためには、適切な治療を継続することがとても大切です。育ち盛りの子どもたちにとって、薬の内服や食事療法などの治療を日々続けていくことは簡単なことではありません。私たちは、治療を続けるためには、子どもたち自身が一つ一つの治療の意味を理解することも重要だと考えています。
そこで、以下に、これまでに当センターで行われてきた主なクローン病の治療についてご説明します。最近は、新たな治療薬の開発が進んでいますが、小児患者に対する使用経験が少ないものもあり、一部、ここでは扱っていないものがあることをご了承ください。
クローン病 各治療の位置づけ

栄養療法について
通常の食事をいったんやめる代わりに、経腸栄養剤を飲んで栄養をとることを栄養療法と言い、クローン病による腹痛や下痢、発熱といった激しい症状は、この栄養療法で大きく改善することが分かっています。
栄養療法には、一日に必要なカロリーの全てを経腸栄養剤で摂取する「完全経腸栄養療法」と、一日に必要なカロリーの約半分を経腸栄養剤で摂取する「部分経腸栄養療法」の二つがあります。
「完全経腸栄養療法」は、ステロイドや生物学的製剤といった免疫抑制薬と同じくらい効果があります。日本国内では、脂質が少なく腸管に負担をかけない成分栄養剤(エレンタール®/エレンタールP®)を使用することが一般的です。当センターでは、子どもに対する有効性と安全性の観点から、クローン病の診断後に2~4週間の完全経腸栄養療法を行っています。その後も、病気の再燃予防のために「部分経腸栄養療法」を継続しています。「完全経腸栄養療法」を自宅で続けることは難しいため、原則入院していただき、多職種で構成されたIBDチームでサポートしながら治療を行っています。子どもたち自身が、完全経腸栄養療法によって症状が劇的に改善することを実感することで、その後の部分経腸栄養療法に主体的に取り組む姿勢が見受けられます。
<成分栄養剤について>
成分栄養剤(エレンタール®)は、消化をほとんど必要とせずに吸収されるため、腸の安静を保つ効果があります。クローン病に対する治療効果のメカニズムについては、ある種のアミノ酸の有効性や、腸内細菌叢(そう)を介した抗炎症作用などが報告されているものの、完全には解明されていません。成分栄養剤は特有の風味があるため、そのままでは飲みづらいのですが、専用フレーバーの使用の他、ゼリーやシャーベットにする工夫を行うことで、ほとんどの子どもたちが問題なく飲めるようになります。ただし、脂質や一部の微量元素が十分に含まれていないため、長期にわたり栄養の大部分を成分栄養剤に依存する場合には、脂質やセレンの補充療法が不可欠です。
薬物療法について
IBDは指定難病で、その患者数も年々増加していることから、新しい研究や薬の開発が盛んに行われています。治療効果の高い薬や在宅自己注射製剤などの出現によって、IBDの患者さんの生活の質(QOL)は確実に向上しています。一方で、使用方法を誤ると重大な副作用を引き起す薬も多くあります。当センターでは、有効性と安全性の最新情報に留意しながら、一人1人の子どもの状態に合った適切な薬剤を選択し、副作用に注意しながら、子どもたちの将来に可能な限り支障を来さない診療を心がけています。
<5-ASA製剤(ペンタサ®など)>
5-ASA製剤は免疫を抑制することなく、腸の炎症を鎮める優れた内服薬です。有効成分が炎症部位で効率よく効果を示すように、薬ごとに様々な工夫が施されています。クローン病では小腸病変にも効果的なペンタサ®が使われます。錠剤が飲めない子どもたちに対しては、顆粒製剤を使うことで服用が容易になります。5-ASA製剤が体に合わず、導入後に腸炎症状がかえって悪くなる場合もあり、その場合は、内服を中止して他の治療薬への変更を考慮します。
<ステロイド (プレドニン®, プレドニゾロン®、ゼンタコート®など)>
ステロイドは炎症を抑える力が強く、即効性があるため、症状が激しいクローン病に対して非常に有効です。多くの場合、つらい血便や下痢といった症状が、短期間に改善します。ステロイドの副作用である満月様顔貌(頬を中心に脂肪がついて顔がまん丸くなること)や多毛といった症状は、使用を中止すれば元の状態に戻ります。しかし、不可逆的な大腿骨頭壊死の他、ステロイドの使用が長期に及ぶと、骨粗しょう症・感染症・白内障・緑内障といった様々な副作用が生じやすくなるため、ステロイドを使用中の患者では定期的にモニタリングすることが重要です。また、特に成長期の子どもでは、成長障害を来すことから、ステロイドの使用が最小限になるように留意しています。
<アザチオプリン(イムラン®、 アザニン®)>
アザチオプリンは免疫調節薬とも呼ばれ、ステロイドなどで腸炎を抑えた後に、寛解状態を維持する効果に優れています。また、後述するインフリキシマブと併用することで、インフリキシマブの治療効果を高めることもできます。白血球数減少や重度の脱毛といった重篤な副作用が一部の患者さんに生じますが、最近の研究で、東アジア人における危険な白血球減少と脱毛の原因となる遺伝子(NUDT-15)が特定されました。当センターでは、アザチオプリンを導入する際にその遺伝子を解析することで、副作用を未然に防ぐことを心掛けています。その他にも、発熱、悪心・嘔吐、下痢、膵炎などの副作用が起こりうるため、導入後に腹部症状や発熱が認められた場合は、アザチオプリンを中止して確かめることもあります。また、極めてまれですが、悪性リンパ腫や血球貪食症候群といった血液疾患とアザチオプリンの関連性が指摘されているため、血液検査などで注意深くモニタリングしています。
<抗TNF-α抗体製剤(レミケード®、インフリキシマブ-BS®、ヒュミラ®)>
クローン病の腸管粘膜において腸炎を起こしている代表的な炎症物質は、白血球が放出するTNF-αです。このTNF-αの働きを抑える薬が開発されたことで、それまで治療に難渋していたクローン病の患者さんにおいても、寛解状態を維持できることが増えてきました。日本でも、6歳以上の小児患者を対象に、レミケードの治験が行われ、子どもに対する効果と安全性が評価された結果、6歳以上の小児患者における使用も認められています。抗TNF-α抗体製剤は炎症を抑える力が強く、長期間にわたる寛解の維持に加え、成長障害を改善する働きもあるため、当センターでは重症の患者さんや長期にわたりステロイドが使用されている患者さんに使っています。クローン病の治療に使用できる抗TNF-α抗体製剤は、病院で8週間隔で点滴をするインフリキシマブ(レミケード®、インフリキシマブ-BS®)と、自宅で2週間隔で自己注射する皮下注製剤のアダリムマブ(ヒュミラ®)があります。当センターでは一人一人の病状や生活の状況に合わせて、使用する薬剤を選択しています。
インフリキシマブは強力に腸炎を抑える効果がありますが、体が薬を異物であると認識すると、治療効果が弱まったり(効果減弱)、投与中に発疹や息苦しさといったアレルギー反応(投与時反応)が生じたりする場合があります。
抗TNF-α抗体製剤を使用している患者さんは、体を病原体から守る免疫の働きが抑制された状態となるため、感染症に注意が必要です。発熱した場合、特にぐったりして全身状態が悪い場合は、早めに受診してください。
抗TNF-α抗体製剤を使用することにより、体の中に潜んでいた結核やB型肝炎が顕在化する恐れがあるため、薬を使用する際には、事前にこれらの感染症が潜んでいないかを血液検査やレントゲン写真で調べています。
<抗IL-12/23p40抗体製剤:ウステキヌマブ(ステラーラ®)>
ウステキヌマブは、前述の抗TNF-α抗体製剤とは異なるはたらきにより、クローン病の炎症を抑える抗体製剤です。白血球を異常に活性化させているIL-12・IL-23という物質を抑えることで効果を発揮します。初回の投与は点滴ですが、2回目以降は皮下注射で8~12週間隔で投与します。当センターでは、主に、抗TNF-α抗体製剤の効果が不十分な場合や、重篤な副作用のため継続が困難な場合に導入されています。投与時反応などの副作用が少ない薬と考えられていますが、頭痛や悪心、上気道感染といった副作用の他に、結核や肝炎などの感染症に注意して使っています。
血球成分吸着除去療法
薬物療法以外の治療法のひとつに、血球成分吸着除去療法があります。肘のところにある太めの血管(静脈)から血液を一旦体外に取り出して、特殊な筒(カラム)を通過させることで、炎症に関与している血液成分を除去する治療法です。薬物療法による治療効果が得られにくい場合や、副作用により薬を使用できない場合に導入が検討されます。通常、1回の治療で2本の点滴が必要ですが、当センターでは体格の小さい小児に対して1本のみの点滴で行う方法をとっています。一週間に1~3回の頻度で、最大10回まで繰り返し施行することが認められていて、徐々に治療効果が得られます。有害事象は比較的軽微な頭痛や寒気・吐き気のみであり、薬物療法の重篤な副作用を心配する必要がありません。ただし、治療に際して血圧の変動が生じることもあります。数回の治療で効果が得られない場合は、他の治療方法に切り替えることもあります。

手術について
近年の薬物治療や内視鏡治療の進歩によって、外科的治療を要する患者さんは少なくなってきています。しかし、病気の症状が重く、薬による病気のコントロールが難しい場合や、薬の副作用により治療の継続が困難な場合には、外科的手術を検討します。
クローン病の診療において最も行われている手術は、痔瘻(じろう)に対する手術です。シートン法といわれる方法は、痔瘻(じろう)にドレーンを通しておくことにより、膿が体の中に溜まらないようにし、肛門周囲膿瘍や痔瘻(じろう)の合併症を防ぐ効果があります。その他、狭窄した部位や、内科的治療を行っても改善が見られない炎症が強い部位が手術の対象となります。
当センターでは、手術を適切なタイミングで提供できるように、外科チームと連携して診療します。特に年長児では、必要に応じて、IBDの手術を専門とする成人IBD診療施設と連携して診療を行うこともあります。

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」(鈴木班)
平成30年度分担研究報告書. 潰瘍性大腸炎・クローン病. 診断基準・治療指針より引用.
日本では、感染症対策上、重要度が高いと考えられるものについては、「予防接種法」という法律に基づいて、予防接種を受けることが推奨されています。予防接種を受けることによって、感染症にかかることを予防したり、かかってしまった場合でも重症化しにくくする効果が期待されます。
炎症性腸疾患の患者さんには、前述のように、腸管で起きている炎症をコントロールするために、免疫の働きを抑える治療薬が使用されることがあります。しかし、免疫は、本来、様々な病原体から体を守る働きを担っていますので、これらの治療薬によって、免疫の働きが弱められることは、病原体に対する抵抗力も弱めてしまうことを意味します。したがって、炎症性腸疾患の子どもたちにとっても、予防接種を行って病原体に対する抵抗力をきちんとつけておくことは、病原体から体を守るために、とても大切なことであると考えられます。
現在、日本で勧められている予防接種には非常にたくさんの種類があります。日本小児科学会から「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」が公開されており、いつ、どの予防接種を受けることが勧められるのか、分かりやすくまとめられていますので、ぜひご参照下さい。(http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/vaccine_schedule_hogosya.pdf)
しかし、免疫の働きを抑える治療薬を使用している場合には、予防接種をする前に、注意も必要です。生ワクチン(BCG、麻疹・風疹、水痘、おたふくかぜなど)には、弱毒化した生きたウイルスが含まれています。免疫のはたらきが一定以上弱められた状態で接種すると、ワクチンに含まれるウイルスによってその病気を発症したり、重篤化したりする恐れがあるため、そのような状態では、原則として生ワクチンの接種は勧められません。その一方で、不活化ワクチン(インフルエンザ、Hib、肺炎球菌、B型肝炎、4種混合、2種混合、日本脳炎、ヒトパピローマウイルスなど)は、病原体となるウイルスや細菌の感染する力を失わせてありますので、ワクチンによってその病気を発症する心配はありませんが、免疫のはたらきが弱められた状態では、ワクチンの効果が少し得られにくくなる可能性があるかもしれません。
どの予防接種をどのタイミングで接種するのが勧められるのかについては、患者さんの年齢や治療内容、その病原体に対する抗体の獲得状況により異なりますので、ぜひ担当医にご相談下さい。
IBDは、慢性疾患で治療が長期に及ぶため、子どもたちは少なからず不安を抱えて生活しています。その不安を少しでも軽減するためには、子どもたちに疾患や治療について理解してもらう必要があります。そして、子どもたちのニーズや疑問に応えながら、一人一人のライフスタイルに合わせたきめ細やかな医療を提供することが重要です。
当センターでは、医師のみでなく、専門性の高い多職種で構成されたIBDチームで診療を行っており、定期的なカンファレンスを通じて役割分担をして、密に連携を図ることで、最適な診療を提供できるように努めています。

定期カンファレンス
看護師
看護師はIBDチームの中でも、入院中の子どもたちにとって最も身近な存在です。特に、入院中の環境を整えるとともに、苦痛や不安を共有しながら、時に励まし、時にいたわり、そして検査や治療を乗り越えた時には共に喜びながら、子どもたちに寄り添います。また、退院後も生活の状況にあった外来診療が自立して行えるように、子どもとご家族に適切な情報を提供するとともに、入院中の状況を病棟から外来の看護師に引き継いでいます。
薬剤師
IBDの治療薬には、毎日服用する薬から、自宅や外来で数週間~数ヶ月に1回、定期的に投与する薬まで様々な種類があります。いずれも"自己判断でやめない"ことが重要です。子どもたちが薬のことを理解して、主体的に治療に取り組めるように、入院したときには担当薬剤師が薬について子どもの成長と発達段階に合わせて説明しています。時にはクイズ形式で、子どもたちが楽しく理解できるように工夫しています。IBDの分野では、新しい治療薬が次々と開発されているため、最新の情報を取り入れながら、一人一人に合った最適な薬を提供できるように努力しています。
栄養士
IBD診療では、食事への配慮が必要になることが少なくありません。特に、クローン病では、脂質の摂取量が多くなると腸炎が悪化しやすいことが知られています。一方で、楽しくバランスのとれた食事は、子どもたちの心身の成長のために重要です。子どもたちが、安全で適切な食生活が送れるように、管理栄養士が病気の状態や年齢に応じた食事療法を分かりやすく説明しています。病気の状態や発症前の食生活を考慮した、その患者さんにあった指導を心がけています。中高生を対象に院内の売店で"模擬買い食い"を行うなど、楽しみながら脂質量が少ない食品を選べる工夫もしています。もちろん本人だけでなく、調理されるご家族を対象に、「食事の留意点」や「調理のちょっとしたコツ」などを具体的に説明しています。管理栄養士による栄養指導は、外来でも受けられ、家庭だけでなく、学校給食や修学旅行での食事についての相談も可能です。
心理士
IBDを抱えながら学校生活を送ることには、心理社会的なストレスが少なからず伴います。日々の内服や定期的な通院に加えて、自由な交友関係や学校行事を諦めなければならないときには、そのストレスがさらに大きくなります。また、診療の中で疲労感と無力感を感じるのは、子どもを支える家族も同様です。治療中の子どもと家族のストレスを少しでも軽減できるように、専属の臨床心理士(公認心理士)が面談や心理テストを通じて心の揺れを評価することで、総合的なケアが行えるような体制を取っています。
チャイルド・ライフ・スペシャリスト
入院した子どもたちは、病院という特別な環境で、痛みや恐怖を伴う検査・処置・治療を受けなければならず、大きなストレスと困難にさらされることもあります。特に幼少期に発症した子どもたちは、なぜ自分が治療を受ける必要があるのか分からずにいます。そのような不安を軽減し、医療体験をプラスの体験に転じるためには、子どもたちの思いや体験に注目して関わり、子どもたちが本来持っている力を発揮できるように支援することが重要です。当センターでは病気を『乗り越える力』を発揮できるようにサポートする国内でも数少ない認定チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS: Child Life Specialist)がIBDチームに加わり、不安やストレスが最小限になるように努めています。
ピア・サポート
通常の診療とは別に、子どもたちとご家族に病気のことをお伝えする機会を設けています。これまでに、サマーセミナーや他病院との協力の下、同世代の同じ病気をもつ仲間たち(ピア"peer")とともに過ごせる場所としての「IBD子どもキャンプ」(リンク:CCFA)を開催してきました。それらを通じて病気を前向きに受け入れることができるようになったという子どもたちの声や、ご家族同士の交流が希望につながったという親御さんの声も頂いています。
トランジション
小児期に発症した子どもたちも、大人になれば生活習慣病やがんといった成人期特有の疾患を念頭においた診療が必要になるため、小児科での診療が難しくなります。
当センターでは、小児慢性特定疾病の対象から外れる20歳前後を目安として、成人診療科への移行を行っています。この移行のプロセスを"トランジション(移行期医療)"と呼びます。トランジションでは、子どもたちが自身の病気や治療について、十分に理解し、主体的・自立的に病気と向き合い、付き合っていけるようにすることを目指した取り組みを行っています。適切なタイミングで相談させていただきながら、成人IBD診療施設と連携を取り、ライフステージに合わせた診療が実現できるトランジションを目指しています。
ドナルド・マクドナルド・ハウス
病気の子どもとそのご家族が利用できる滞在施設で、国立成育医療研究センターに隣接しています。特に、遠方からの受診や入院の際にご利用いただくことが可能です。
小児慢性特定疾病について
IBDは小児慢性特定疾病の対象となります。18歳未満の小児IBD患者が申請でき、認定されると20歳になるまで医療費の助成が受けられます。また、小児のIBD患者さんの実態を把握し、さまざまな研究活動や子どもたちの特性を踏まえた健全育成・社会参加の促進、地域関係者が一体となった自立支援の充実をはかるための大切な資料にもなります。20歳以降は、指定難病として、医療費の助成を申請することができます。医療費の助成は申請後から適応になりますので、IBDの診断を受けた方は、お早めに申請されることをお勧めします。
研究
子どもの頃に発症するIBD患者さんは、年々増えています。この傾向は世界共通で、世界中の様々な研究機関がIBDの診断・治療をより良くするための研究にいそしんでいます。私たちも、小児IBD診療をより良くするための研究を複数行っており、その結果を患者さんやご家族に還元していけるように努力を重ねています。
当センターを受診されている子どもたちやご家族には、研究や治験について、適宜ご案内させていただいております。ただし、研究へのご参加は、あくまで自発的な意志に基づくものです。ご協力の可否によるその後の診療へ影響はございません。説明を十分に聞いていただいた上で、可能な範囲でご協力をお願いできれば幸いです。
受診方法
外来は、救急センターを除いてすべて予約制ですので、当院で受診される方は『事前予約』が必要です。
国立成育医療研究センターでは、事前予約制を導入しております。当院での受診を希望の方は他院からの診療情報提供書(紹介状)をお手元にご用意の上、予約センター(電話 03-5494-7300)で予約をお取りになってからご来院ください(予約取得時に、紹介状の確認をしております)。紹介状をお持ちでない場合、別途選定療養費がかかります。詳しくは、予約センターにお問い合わせください。
なお、緊急で受診が必要なときは、現在かかっている医療機関の医師から直接、医療連携室(TEL:03-5494-5486 (月~金 祝祭日を除く 8時30分から16時30分))へご連絡をお願い致します。
 予約センター(代表)
予約センター(代表)
03-5494-7300
月~金曜日(祝祭日を除く)9時〜17時
医師紹介
治験について
医療従事者の方へ
診療実績
小児炎症性腸疾患(IBD)
-
クローン病について